LD (学習障害)/ SLD(限局性学習症)とは、発達障害*の一種で特性として学び方の特異性があげられます。
「日常生活はスムーズに送れているのに、なぜか勉強だけはどんなに頑張っても難しい…」という方はLDの可能性があります。では、LDとは「勉強のできない障害」なのでしょうか?
答えは明確にNoです。
LDとは「Learning Disabilities(学習障害)」の略ですが、最近では「Learning Differences(学び方のちがい)」や「Leaning Diversity(学び方の多様性)」と定義できないか、というお話があります。
つまりLDとは、決して勉強のできない障害ではなく、大多数の人とはちがう学び方の方がフィットしやすい人たちのことを指します。
では、どんな学び方がいいのか?それは人によって異なるため、きちんと検査をして自分の得意・不得意を理解しながら対応していくことが大切です。
★「読み」の苦手さ
・読むことがすごくゆっくり
・スムーズに読めずつっかえたり読み飛ばしたりする
・読んで理解することが大変で頭に入らない
・日本語は読めるが英語を読むことが極端に辛い
★「書き」の苦手さ
・丁寧に書いても読みづらい字になる
・書き間違いが多い
・漢字を書くのがおっくう
・文法を間違える
・英単語のスペルが覚えられない
★「計算」の苦手さ
・数字の大小がわからない
・暗算が大の苦手で計算に時間がかかる
・筆算も嫌い
・分数などの概念の理解が難しい
少し前ですが、2012年の日本で『小学生の4.5%が学習面で著しい困難を示している』という調査結果がでました。

「学習面で著しい困難」=「LDである」とは必ずしもいえませんが、学習に関して特別な支援を必要としている人は決して少なくないことがわかります。
また、この調査の中では、特別な支援が必要と考えられるような困り感のある子どものうち、実際に支援を受けているのは約半数程度であると示されており、学校における学びの多様性への対応はまだまだ発展途上であるといえます。
【参考】文部科学省 通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について 2012年
脳のどういった機能のちがいが、学びの多様性を生み出すのかその一部を解説します。
人は、情報の8割を視覚から得ているといわれています。そして、LDの人の中にはこの「見て理解する力」が他の人とちがうことがあります。
例えば目玉の運動能力(衝動性眼球運動)が弱い人は、視線をジャンプさせることが得意ではありません。そうすると、教科書を一行ずつ順番に読むことが難しくなるため、音読が苦手になる可能性があります。

その他にも見ているものの「形を理解する力(形態知覚)」や「位置や方向などを把握する力(空間知覚)」といったものもあります。こういった力に弱さがあると、文字の読み書きや、記号・地図・グラフなどの意味を理解したり記憶することが難しくなります。
「読むのや書くのが苦手だったら勉強なんかできないよ!」と思うかもしれません。が、そんなことはありません。
世界はIT技術のおかげでとっても便利になりました。例えば教科書が読めなくても読み上げてくれるアプリや、文字が書けなくてもタブレットや音声入力を使って表現ができる時代です。積極的に便利ツールを使って、あなたにフィットした『最先端の学び方』を探しましょう。
ワーキングメモリーというものがあります。これは、「何かを覚えておきながら別のことを考えても、覚えていた内容を忘れない能力」のことです。
例えば、「100円のリンゴを3個と、50円のみかんを4個買ったら合計いくら?」という問題をだされたとします。
まず100×3の計算をし、その答え(300円)を覚えておきながら、次に50×4=200をして、300と200を足して…というように、途中ででてきた答えや、次の計算に使う数字を覚えておくためには、このワーキングメモリーという能力が必要となります。
このワーキングメモリーの容量が大きくないタイプの人は、ノートテイクや計算が難しく、効率よく勉強することが苦手になります。
いちいち紙に書きだして、覚えておく量を極力少なくする、というのもひとつの方法です。書くことに苦手さがある場合は、板書を写すときはタイピングを使ったり、カメラを使う方法もあります。計算については電卓や計算アプリを活用していくこともできます。

【参考】Photomath
協調運動とは、丁度いい強さや方法で、身体を動かす能力のことをいいます。
この協調運動は『粗大運動』と『微細運動』に別れます。
粗大運動に苦手さがあると、姿勢を保つことが難しくなり、授業中長時間座ることが大きなストレスになり、学習への集中がしづらくなります。
微細運動に苦手さがあると、目と手が協力しながら動くことが難しくなるため、文字が崩れる・ゆがんだりはみ出たりする、力が入りすぎて疲れやすくなる、というように「書くこと」の困難に繋がります。
「不器用さなんて変わらないよ!」と思ったあなた。大丈夫です。世界には便利なグッズがたくさんあります。
書くことの苦手さは上でご紹介したようなツールが使えます。また、姿勢を保つためには専用のクッションなどがあります。自分にあったものをうまく活用して、苦手を補いながら本来の力を引き出そう!
LDの方が勉強が苦手なのは努力が足りないのではなく、その人にあっていない学習方法が原因で起こっています。つまり、努力だけでは解決ができません。
例えば同じ「文字を書くことが苦手」でも、見ることに苦手さがあるのか、運動に苦手さがあるのかによって対処方法が変わります。どんな方法が自分にピッタリ合うのかは、専門家からの検査を受けて見ることをおすすめします。
アセスメントはクリニックや支援センターなどで受けることができます。まずはかかりつけのお医者さんに相談をしてみましょう。

自分自身の感覚はその人だけのものであり、他の人がすべてを理解することはできません。
特にLDの人特有の情報処理の能力は、発達障害でない人(定型発達と呼びます)の人にとって、なかなか理解がしづらい部分があります。
特に、特性に合わせて苦手を補うためのツールを使うことに抵抗感を覚える人は残念ながらまだまだたくさんいます。ですが、苦手なことを便利な道具をつかって本来の力を発揮するということは、とてもあたまのいいやり方です。あなたには学ぶ権利があって、そのために必要な工夫をすることを反対することは誰にもできません。
そのため、まずはあなたがその感覚を持ったうえで、自分の特性と、どんな配慮が必要なのかを説明できるように練習をしたり、説明のためのシートを用意できるとよいでしょう。
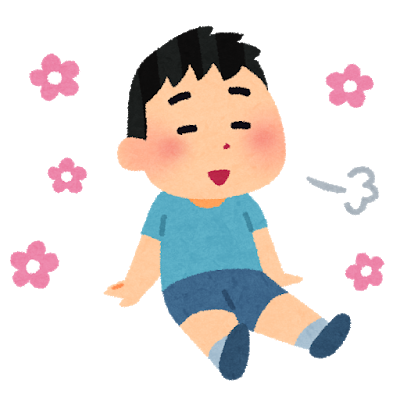
LDの方は、”多数派”の学び方に合わせる機会がどうしても多く、心や体が疲れやすい人もいます。
自分の好きなことや興味のあることを思っきり楽しむ機会を意識的につくるなど、上手にリラックスできる方法を探しておけるとよいでしょう。

どうすれば自分自身の強みや個性を活かせるのか?どうしたら困りごとや悩みを解消できるのか?
発達障害のある・なしに関わらず、自分一人でなにかを解決することは難しいです。上手に人に頼る力をつけるためにも、信頼できる人に相談するスキルを身につけていきましょう。
親御さんや担任の先生など、身近な人に相談しづらい場合は、学校のスクールカウンセラーの先生に相談してみることをおすすめします。
※近くに相談先できる人がいない場合は…
24時間子供SOSダイヤル ☎0120-0-78310(文部科学省HPより)
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます