ティーンズ御茶ノ水です。
今回は、目黒駅徒歩3分にある「救急医のいる町のお医者さん ひでまるファミリークリニック」の3名の先生にお話を伺いました。

| 所在地 | 〒153-0063 東京都目黒区目黒1-4-11 NTビル1階・2階・4階 |
| 電話番号 | 03-3493-9901(代表) 090-6365-9437(小児科) |
| ウェブサイト | https://hidemaru-clinic.com/ |
| ✅ 地域に根ざした救急総合診療クリニック ✅ 年齢性別、国籍、診療科を問わないボーダレス診療 ✅ 夜間・休日は全科「救急外来」で対応! |
―― はじめに院長の市丸 秀章(いちまる ひであき)先生からお話を伺います。
市丸先生 院長の市丸秀章です。私は10年以上大学病院救命救急センターで診療に携わり、多くの救急症例やその後の集中治療、そして社会復帰までの医療現場を経験してきました。
その経験を活かした形で、地域に根ざし日常の健康トラブル解決に貢献したいという想いから、2021年1月に「ひでまる救急クリニック」を開設。2023年8月からは小児科の専門外来も常設し、現在の「ひでまるファミリークリニック」に改名しました。
現在は、年齢や性別、国籍、診療科を問わない「救急総合診療クリニック」として、地域の皆さまに信頼される存在を目指し、日々努力を重ねています。どうぞよろしくお願いいたします。
―― 救命救急という厳しい現場でご尽力されてきたこと、心から尊敬いたします。どのような想いがあってひでまるファミリークリニックを設立されたのでしょうか?
市丸先生 長きにわたる救急の現場経験を通して、単に命を救うだけでなく、一人ひとりの社会的背景や生活環境を理解すること、社会や倫理的側面にも十分配慮して医療にあたることの重要性を学ぶことができました。医療は単なる治療行為にとどまらず、一人ひとりの人生や、地域社会全体に深く関わるものなのだと考えています。
そのような経験から、地域という単位ごとに、どんな人でも気軽に安心して訪れることができるクリニックが必要だと強く思うようになりました。
地域性や国籍、そして生活環境を理解して寄り添ってくれるような「かかりつけ医療」を受けられる環境を整えることで、地域の皆さんが安心して生活できる社会が実現できると考えています。夜間や土日といった時間帯にも診療をする決意をしたのもそれが理由です。
こうした誰もが安心して暮らせる社会の実現に貢献したいという想いから、地域に根ざしたクリニックづくりを目指し、ひでまるファミリークリニックの設立に至りました。

―― 救命救急という命の現場で、真摯に命に向き合って来たからこその想いなのだと感じました。
市丸先生 クリニックのスタッフは私同様に救急医療現場出身者が多く、様々な症例に真剣に向き合ってきたからこそ得られた多様性への懐の深さに自信を持っています。
理解して寄り添うことの大切さは診療所でも同様です。例えば発達に特性のあるお子さんの中には、風邪をひいたときなどクリニックの待合室で順番を待つことが大変な方もいらっしゃいます。ひでまるファミリークリニックは、そのようなお子さんとご家族が安心して来ていただけるよう、スタッフも日々勉強しています。
児童精神科が専門ではありませんが、風邪やケガの診察、あるいは発達相談を気軽にできるクリニックが1か所でも増えることで親御さんの負担も減るのではと考えています。その意味でも「ボーダレス」に医療を提供できるクリニックを目指しています。
―― この記事を読んでくださる方にとっても、心強く感じていただけると思います。
―― つづいて小児科部長 かぶらき(鏑木) 陽一郎 先生からお話を伺います。
陽一郎先生 小児科部長のかぶらきです。
私は東京女子医科大学小児科に15年間勤務したのちに、2023年から地域に根差した医療を目指すべく目黒の地で小児診療を始めました。大学では消化器疾患(おなかの病気)を専門としつつ、小児科専門医として幅広い疾患に携わってまいりました。また消化器疾患を診療する過程で、お腹以外の幅広い症状について診療する機会も多くありました。消化器の不調は、生活習慣や心の状態、成長・発達の状況と深く関わっております。単にお腹の症状を治すだけではなく、その背景にあるさまざまな要因を丁寧に探ることが大切であることを、消化器疾患というフィルターを通じて学ばせていただきました。
お子さまの病気だけでなく、ご家族や生活環境にも目を向けた医療を提供することが当クリニックの使命だと考えております。他の医療機関との連携もスムーズに行えるよう努めていますので、どうぞお気軽にご相談ください。笑顔でお迎えいたします。
―― まず、小児科診療の特徴について詳しく教えてください。
陽一郎先生 小児科専門医として、風邪症状や嘔吐下痢といった感染症から、皮膚症状や栄養、発育などの問題、アレルギー症状、その他、ちょっとした疑問点や悩みについても診療してております。
当院では、お子さんとご家族のお話をじっくり伺い、必要に応じて専門的な検査や他科との連携を行いながら、成長発達や生活全体を見渡した診療を心がけています。また、アレルギーや栄養の課題、学校生活や家庭での困りごとにも目を向け、子どもたちが健やかに育つお手伝いをしてまいります。
こどもの病気だけでなく、こどもの周りの人々や生活にも心を配る医療を提供したいという思いを持ってこのクリニックでの診療を行っております。
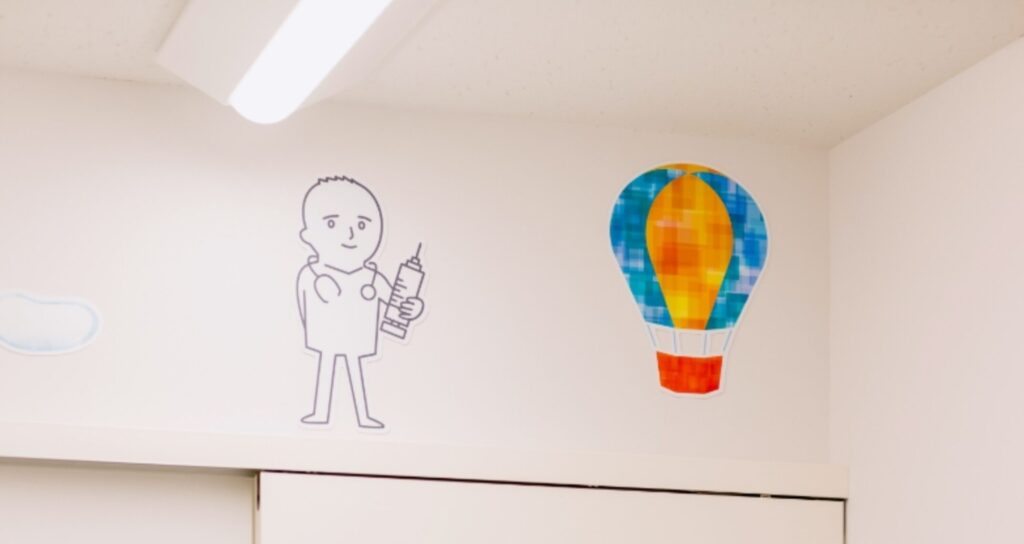
―― 小児の消化器疾患(お腹の病気)がご専門で「うんち外来」もされているのですね。発達障害に腸内細菌が影響しているというネット記事を見たことがあるのですが、先生はどのようにお考えでしょうか?
陽一郎先生 確かに論文を1つ1つ読むと関連がありそうだとは思うのですが、発達障害でお困りの方に対して「どうすればいいか」という答えまでは出ていない、研究ベースでの報告にとどまっている、という認識です。自閉症の子どもは腸内細菌の多様性に乏しく、腸内細菌の産生する短鎖脂肪酸が少ないとの報告がありますが、それが自閉症の原因なのか、結果によるものなのかもわかりません。また、腸内環境が変化する要因は多様であり、一つの因子を改善して改善するものでもありません。
さらに、腸内細菌は60兆個~100兆個いると言われています。そんな膨大かつ多種多様な細菌が、相互に影響を与え合い、動的平衡を保っているのが腸内環境です。世界の人口は80億人を超えていますが、60兆人が住んでいる世界で起きている問題をなくすことがどれだけ難しいかを考えれば、腸内の複雑さがイメージいただけるのではと思います。
―― 先生が担当されている、発達・育児相談外来について教えてください。
陽一郎先生 発達・育児相談外来では、お子さまの発達に関するご相談を承っています。
私は児童精神科の専門医ではありませんが、児童精神科の専門医がいる施設は、全国的に予約がとても取りにくい状況が続いています。そのため、「発達障害かもしれないけれど、相談したほうがいいのかな?」とか、「発達検査ってどんなもの?本当に必要なのかな?」と迷われているご家族も多いのではないかと思います。あるいは、専門のクリニックは少し敷居が高く感じられたり、やっと予約が取れて受診しても「経過を見ましょう」と言われてしまい、不安に思われることもあるかもしれません。
そうした状況の中で、小児科医として、まず発達障害についての基本的なことや、検査や経過観察の意味について、わかりやすくお伝えすることが大切だと考えています。発達の評価は一度で決まることばかりではなく、時間をかけて様子を見ながら判断していくことも多いです。
もし発達の評価が必要かなと思った場合には、院内でも検査が行るので、公認心理師や看護師と相談しながら、どのタイミングでどんな検査を受けるかを一緒に考えています。必要に応じて、専門の医療機関へのご紹介も行っています。
―― 院内の連携だけでなく、他の医療機関との連携も大切にされていらっしゃるのですね。
—— ここからは、かぶらき(鏑木) まきこ先生に伺います。
まきこ先生 発達検査を担当する、かぶらき(鏑木) まきこです。
私はこれまで中学高校のカウンセリングセンター、単科の精神科病院の現場を経て、10年以上、総合病院の小児科・NICUで臨床心理士・公認心理師として働いてまいりました。地域の中で、これまでの経験を活かしてお子さまの目線、ご家族の目線、それぞれの目線に立ちながら、すこやかな子育てのヒントを一緒に考えていけたらと思います。どうぞよろしくお願い致します。
—— 「こども発達検査」について概要を教えていただけますか?
まきこ先生 はい。まずこどもの発達検査には大きく分けて2種類あります。1つは乳幼児を対象とした、運動面の発達も含めた全般的な発達検査。もう1つは、言葉でのやり取りや手作業を通じて認知面や言語面を見る知能検査です。
—— 発達検査は乳幼児健診とは違うのでしょうか?
まきこ先生 乳幼児健診の中では、小児科医が運動面、言語面、精神面の発達を問診と身体診察でチェックしていきますが、次に挙げるような詳細な発達検査は、通常、医療機関をはじめとした専門機関で個別に行われます。健診で何か気になる点があった場合に、より詳しく見ていく方法に医療機関等での発達検査があります。
▼発達検査の種類
まきこ先生 主な発達検査としては新版K式発達検査、遠城寺式乳幼児分析的発達検査、Bayley-Ⅲ乳幼児発達検査などがあります。主な知能検査ではWISC-Ⅴ知能検査、KABC-Ⅱアセスメントバッテリー、田中ビネー知能検査Ⅵなどがあります。また、そのほかに、「読み」・「書き」に困難を抱えるお子さんを対象として、現在の「読み」・「書き」の正確性や流暢性について、どの程度の水準にあるのかを測定して、今後の支援に活かすための検査として、URAWSSⅡ、STRAW-Rといった検査があります。当院でも、WISCだけでは把握しきれない「読み」・「書き」の状態をさらに詳しく検査してほしいというニーズが多く、この10月から「読み」・「書き」のスクリーニング検査を開始します。
▼どんなときに検査を検討するか
—— 発達検査を検討する時期について教えてください。
まきこ先生 お子さんの発達が気がかりなとき、例えば言葉の発達が気になる、集団生活に馴染めない、怒りっぽい、癇癪がひどいなどの状態が続いている場合に、発達検査を検討しても良いかもしれません。

—— 検査に漠然とした不安を感じる親御さんもいらっしゃると思います。そういった方へのアドバイスはありますか?
まきこ先生 発達検査は特別な病気を診断するためのものでも、マイナスのレッテルを貼るものでもありません。また、この検査によって診断名や障害名がつくわけではありません。診断はあくまで医師が診察した上で総合的に行うものです。検査結果は参考にはしますが、それだけで診断が下されるわけではないということを理解していただければと思います。
また、数値などの結果を見て「これは異常なのか、正常な範囲なのか」とよく聞かれますが、そういう視点よりも「お子さんの得意・不得意はどんなことで、どんな特徴が日常生活の中であらわれやすいのか」、「強みを活かして弱みをサポートするにはどうすれば良いか?」、「お子さんのためにできることは何か?」ということを、検査の結果を手掛かりにして一緒に探していく、という姿勢が大切だと思います。
発達検査は、お子さんにふさわしい環境を整えたり、適切な対処法を見出したりするためのヒントを得るものです。お子さんが健やかに過ごせる生活環境を作っていくための手段として検討していただけると良いと思います。
▼発達検査はどこで受けられるか
まきこ先生 大きく分けて、公的機関と民間機関があります。公的機関は原則無料で、発達障害者支援センター、児童相談所、療育センター、教育センター、教育相談所、保健センターなどがあります。ただし、希望者が多いため、受検までに時間がかかることがあります。
民間機関は有料で、地域のクリニックや総合病院の小児科、児童精神科、小児神経外来、民間の療育相談機関やNPO法人などで受けられます。医療機関の場合、保険適用内か外かで費用が大きく異なります。
▼検査を受ける前に確認すべきこと
—— 発達検査を受けるときに気を付けたほうが良いことを教えてください。
まきこ先生 検査を受ける前に確認すべき点として、費用の目安、待ち時間、検査と結果報告面接の所要時間、結果が出るまでの時間、検査結果の伝達方法などがあります。また、検査を受けたいと思った理由や、日常生活におけるお子さんの現在の状態で気がかりな点をしっかり伝えることが大切です。検査者もこの情報を得ることにより、これらの視点を頭におきながら検査をすることで、検査結果から、より具体的な日常生活へのアドバイスをフィードバックできるようになります。
▼検査結果の活用法
まきこ先生 検査結果は、お子さんを取り巻く人々と共有することが重要です。幼稚園・保育園や学校の先生、特別支援学級の先生、スクールカウンセラー、養護教諭などと共有し、個別指導計画や個別支援計画の作成に活用してもらうといいでしょう。
具体的な配慮の例としては、「耳からの情報より目からの情報の方が理解しやすいので、課題や持ち物は黒板にも書いてください」、「タブレットで黒板を撮影することを許可してください」、「書くスピードが遅いため、書き取りの回数を減らしてください」などがあります。スクールカウンセラーと協力して、結果の伝え方を検討するのも良いでしょう。
—— 具体的な例をありがとうございます。合理的配慮の伝え方は難しいという声をよく聞きますね。
まきこ先生 はい、多くの方がここで困っているようです。具体的な配慮の方法を伝えることが大切ですね。ひでまるファミリークリニックでは、現在のお子さんを取り巻く環境を伺いながら、検査結果から得られた情報をもとに、なるべく具体的に日常生活において工夫すると良い点をお伝えしています。その中で、学校の先生方やお稽古・塾の先生方へ、どのように必要な配慮についてお伝えすると良いのかについても、保護者の方と一緒に考えていきます。
—— 最後に保護者の方へのメッセージをお願いします。
ひでまるファミリークリニックは、お子さんとそのご家族に寄り添った医療を今後とも展開していきたいと思っています。2024年から始まった発達検査についても、ささいなことでもかまいませので、ぜひご相談いただければと思います。
—— ありがとうございました。
『ご利用までの流れ』のページへ移動します