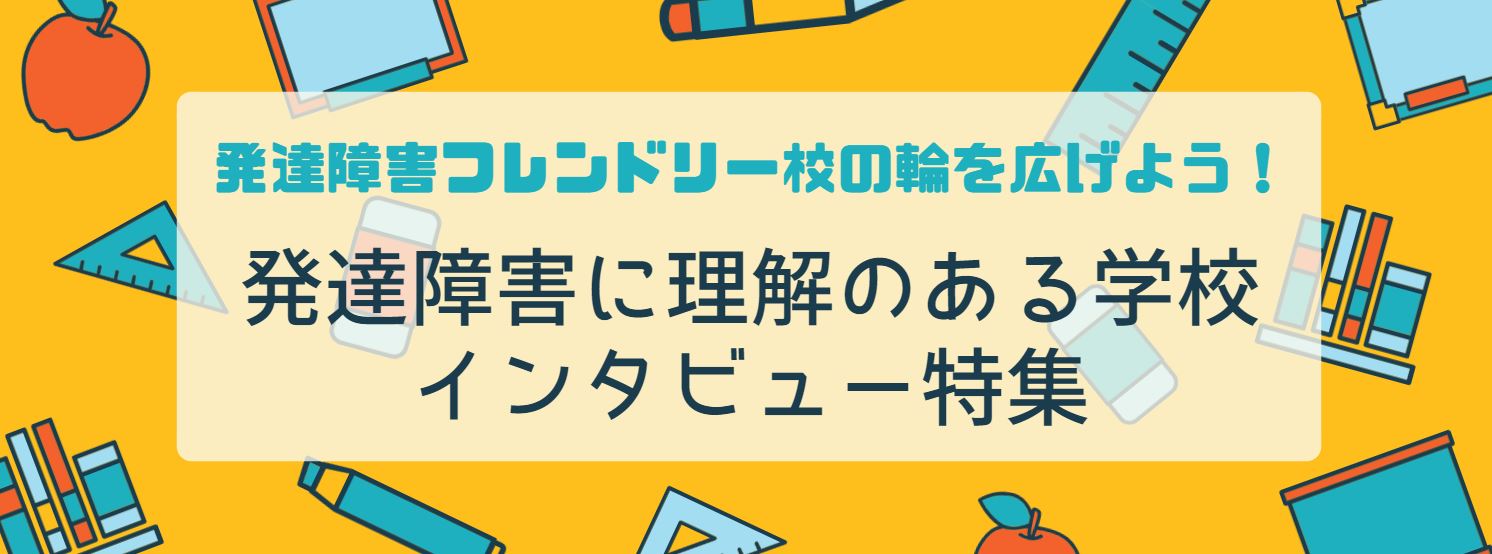
こうした毎日のやりとりは、子どもたちの「メタ認知(=自分を客観的に見る力)」を育てます。例えば、「自分はどんな行動をとったか」を自分で言語化できるようになると「あ、次はこうすればいいんだ」と前向きに考えられるようになるのです。
これは、困りごとを“教員や親に言われて気づく”のではなく、“自分で気づいて調整できる”ようになるということ。大人になったときにも生きる、非常に重要な力です。
この仕組みのもうひとつの特徴は、“保護者ともつながれる”ことです。生徒が学校で記入した内容や、教員のコメントは、保護者のスマートフォンにもリアルタイムで届きます。
その日の夕方、「今日は“いいね”がついてたね。どんなことがあったの?」という会話が、自然に家庭で始まるのです。
これまでなら、「学校で何かあったみたいだけど、子どもが話したがらない…」「学校からは何か問題があった時にしか連絡がこない」といったすれ違いがありましたが、日々のやりとりが見えることで、生徒・保護者・教員が“同じ地図”を見て支援できるようになります。
この取り組みの最終的なゴールは、「子ども自身が、自分の特性や苦手なことを言葉にできるようになる」こと。進学先の先生に「私はこういうことが苦手なので、こういう配慮があるとうれしいです」と伝えられるようになることです。
「そのときが来たら、『この子は卒業しても大丈夫』と思えるんです」
『ご利用までの流れ』のページへ移動します
ティーンズでは発達凸凹の子どもたちの進路選択の幅を広げるべく「発達障害*に理解のある学校」の情報を集めています。
「我こそは発達障害フレンドリー校だ!」という学校関係者のみなさま
「わたしの通う学校こそ発達障害フレンドリー校だ!」という在校生・保護者のみなさま
「この学校について詳しく取材してほしい!」という受験生・保護者のみなさま
ぜひこちらのページで紹介させてください。情報をお待ちしております!
✉teens@teensmoon.com (学校インタビュー担当 宛)
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます
インタビュアーより
今回のインタビューでは個別の支援計画に特化してブログを書かせていただきましたが、その他にも星槎高校のSSTの授業やキャリア学習についてもお話を伺いました。
どのお話からも星槎高校は、発達障害のあるお子さんにとって「ただ居場所がある」だけでなく、「自分を理解し、強みに気づいていける」そんな貴重な学びの場であると強く感じました。
今回は貴重なお話を聞かせていただきまして、ありがとうございました。