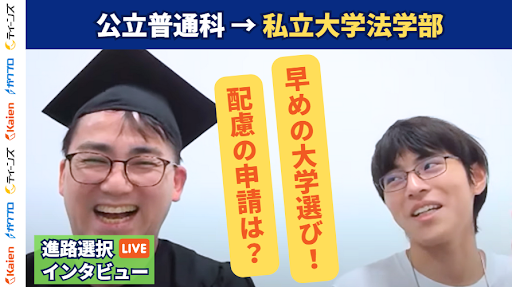

Rさんプロフィール
Rさんは現在、私立の4年制大学・法学部に通う1年生。高校を卒業してから大学生活をスタートさせたばかりですが、その経験を通して進路選びや学びの工夫についてたくさん語ってくれました。
『ご利用までの流れ』のページへ移動します
インタビュアー:Rさん、今は大学1年生ですよね。大学選びって、高3の夏だけじゃなくて高1・高2のときも大切だと思うんですけど、実際どんな風に準備してましたか?
Rさん:自分は母の勧めもあって、高1から動き始めてました。早めに目安を持っておいた方が、高3になったとき余裕をもって勉強できるかなと思って。だから実は高3の夏は、オープンキャンパス1つしか行ってないんです。
インタビュアー:えっ、高3では1つだけ?
Rさん:その代わり高1のときにめちゃくちゃ行ってました。その中で信頼できる友人や学校の先生にも相談して、自分の特性を踏まえた上でどんな大学が合うかを考えていました。
インタビュアー:大学を選ぶときに、ここは譲れないっていうポイントはありましたか?
Rさん:当時は公務員を目指していたので、法律を学べるところが必須でした。あと、もし夢が変わっても他の進路につなげられるような幅広い学びができる大学を探しました。
インタビュアー:なるほど、学べる内容が一番大事だったんですね。他にも見ていたポイントはありますか?
Rさん:はい。自分の特性上、4年間ちゃんと通えるかどうかが大事だったので「交通の便がいいこと」と「キャンパスの雰囲気や環境が快適か」を重視しました。きれいさも大事でしたね。やっぱり汚いと気持ちが下がっちゃうので(笑)。
インタビュアー:オープンキャンパスでは支援室にも行ってたんですよね?
Rさん:そうですね。母が一緒に行って、支援室の人と相談してくれてました。そのとき自分も話を聞いて、「どんな支援が受けられるのか」「自分の大学生活を想像しやすいか」を確認しました。スタッフの方が親身に対応してくれて、安心感がありました。
インタビュアー:これから大学を探す人に向けて、「オープンキャンパスでここをチェックするといいよ」ってポイントはありますか?
Rさん:人によると思うんですけど、自分にとってモチベーションを保てるポイントが大事だと思います。食堂でも図書館でも、友達ができそうかでも、サークルでも。4年間続けられるかどうかを考えて見るのがおすすめです。
インタビュアー: Rさんは最終的に総合型選抜で受験したんですよね。準備や行動で、良かったことや大変だったことはありますか?
総合型選抜とは?:学力だけでなく、経験や能力、学習意欲などを総合的に評価する入試方法。詳細はこちら
Rさん:総合型を受けると決めたのは、高3になってからでした。少しギリギリでしたね。きっかけは塾の先生に「総合型で受けてみないか」と言われたことです。それで調べて、今の志望大学を総合型で受けることにしました。
インタビュアー: なるほど。実際の試験内容はどんな感じでしたか?
Rさん:自分が受けた大学は、書類選考に加えて「面接」と「グループディスカッション」がありました。塾で書類や面接の指導をしてもらいながら準備しました。
インタビュアー:グループディスカッションは緊張しませんでしたか?
Rさん:あまりしませんでした。もともと人見知りしないタイプで、人と話すのも得意だったので。生徒会もやっていたので、その経験をアピールポイントとして使えたのも大きかったです。
インタビュアー: なるほど。じゃあ、高校でやってきた活動も活きたわけですね。
Rさん:そうですね。生徒会に入ったときは単に「やってみようかな」くらいの気持ちでしたけど、結果的に経験が総合型での武器になりました。書類や面接でも「自分をどう伝えるか」という練習になっていたと思います。
インタビュアー:合理的配慮は使いましたか?
Rさん:自分は必要なかったです。人前で話すことに苦手意識がなかったので。ただ、人によっては待機中に別室を希望するなど、配慮をお願いすることはできると思います。
※合理的配慮とは?:日常生活での困り感のある人たちの要望を受けて、社会の中にあるバリアをとりのぞくことをいいます。詳細はこちら
インタビュアー: 確かに。総合型選抜って大学によって内容が全然違いますよね。
Rさん:そうですね。小論文を課すところもあれば、課題提出が必要な大学もあります。中には一発勝負で数学だけ、なんてケースもあるので、受けたい大学がどんな方式なのかは事前に調べておくのが大事です。
インタビュアー: 自分に合った方式を選んだのが、Rさんの成功の秘訣だったのかもしれないですね。
Rさん:自分は「短距離走タイプ」で、長くコツコツよりも一気に集中して頑張る方が合っていたので、総合型は向いていました。一般入試の長期戦は正直きつかったと思います。
インタビュアー:試験はいつ頃だったんですか?
Rさん:エントリーは9月からで、10月に試験、11月の頭には合格が決まりました。
インタビュアー:じゃあ早めに進路が決まったんですね。
Rさん:はい。だから高校3年の後半は、大学入学に向けた準備に時間を使うことができました。
インタビュアー:受験のときには合理的配慮は使わなかったと聞きましたが、大学入学の段階ではどうでしたか?
Rさん:入学前に一応申請しました。
インタビュアー:具体的にはどんな準備をされたんですか?
Rさん:正直、親の方が自分より理解していて、任せきりになってしまった部分も多かったです。でも将来のために自分も少しは参加しました。例えば、高校のときと同じように「試験での配慮をどうするか」とか「課題やノートの取り方」を話し合いました。実際に申請したのは、『ノートをPCで取ることの許可』『定期試験での配慮』『プリントを紙で配布してもらうこと』などです。
インタビュアー:なるほど。そうした配慮の希望は、どこに伝えるんでしょうか?
Rさん:大学には「障害学生支援センター」や「障害支援窓口」があるので、そこに相談します。あと、授業が始まってからは担当教授に直接お願いに行きました。
インタビュアー:入学前から相談できるんですね。
Rさん:はい、窓口には事前に行けます。ただ教授にお願いするのは授業が始まってからです。うちの大学では支援窓口が文書を作ってくれて、それを持って各教授に説明に行く形でした。ちょっと面倒ですけど、ないよりはずっといいです。
インタビュアー:教授へのお願いは自分で行かないといけないんですね。
Rさん:そうです。全部代わりにやってくれるわけじゃないので、自分で頑張って行かないと。先生の居場所がわからなかったり、不在のこともあって大変でしたけど…。
インタビュアー:実際にお願いしてみて、どうでしたか?
Rさん:まだ全員には渡せていないんですが、多くの先生は「こうすればいいのね」と受け入れてくれて、授業を受けやすい環境になっています。
インタビュアー:拒否されることはありませんでしたか?
Rさん:ないですね。もし「うちではできません」って言われたらどうしようって思ってましたけど…。むしろ、法学部の事務員さんがとても協力的で、仲介役になってくれたこともありました。支援窓口だけじゃなく、事務の方がサポートしてくれるのはありがたかったです。
インタビュアー:良い大学に出会えましたね。
Rさん:そうですね。恵まれていると思います。
インタビュアー:今は小学生や中学生のお子さんを持つ親御さんがこの記事を見ているかもしれません。今回のテーマは「夏」ですが、夏以外でも役立つことや、夏だからこそやっておいた方がいいことはありますか?
Rさん:自分が言える立場じゃないかもしれませんが……夏はやっぱり遊ぶことも大事だと思います。本気で遊ぶと気分転換になるので。でも、そのうえで勉強は「やらされる」のではなく「自分がやりたいからやる」という意識で取り組むと気持ちが少し楽になるんじゃないかと思います。
インタビュアー:受験を意識すると、やはり準備は早い方がいいですか?
Rさん:そうですね。早めに動いた方が後々楽になります。自分も高1・高2の頃からオープンキャンパスに行っていました。そうすると、入試や奨学金の手続きも見えてきます。でも正直、そういう手続きは自分だけでは難しい部分が多くて、親のサポートが必要でした。だからこそ、親にちゃんと伝えることが大事でしたね。
インタビュアー:「今からじゃ遅い」と思ってしまう方もいると思います。
Rさん:遅いなんてことはないです!今からでも間に合うことはたくさんあります。親の力を借りつつ、少しずつ自分でできることを増やしていけば大丈夫だと思います。実際、自分もまだ親に助けてもらっていますし(笑)。恥ずかしいことじゃなくて、ありがたいと思って頼ればいいんです。
インタビュアー:親への感謝、大事ですね。
Rさん: ほんとにそうです。中高生になると親と距離をとりたくなる気持ちも出てきますけど、最後に受け止めてくれるのはやっぱり親。自分はすごく感謝しています。
インタビュアー:夏だからこそ挑戦してほしいことはありますか?
Rさん:あります。小さなことでもいいので、チャレンジする経験を積んでほしいです。自分は春に政治関係のインターンに参加したんですが、そういう体験って受験のときにも役立ちますし、自信にもつながります。お仕事体験でもボランティアでも、夏の間にやってみるといいと思います。
インタビュアー:将来の方向性が決まっていれば関連したイベントを、まだ迷っているなら興味のあることに手を伸ばしてみる、ということですね。
Rさん:夏は時間があるからこそ、自分を試せる時期だと思います!
『ご利用までの流れ』のページへ移動します
ティーンズスタッフからのコメント
Rさんは「大学選びは高3の夏だけでなく、高1・高2からの準備が大切」と話してくれました。法律を学べることや通いやすさを重視し、支援室も確認。総合型選抜では生徒会活動などを活かし、早めに合格をつかみました。入学後は支援窓口に相談し、教授にも自分で配慮を伝えて環境を整えています。 Rさんの体験から、進路準備は「早めの行動」と「自分に合った方式を選ぶこと」が大切だと分かります。また、親や大学のサポートを借りながら、自分で少しずつできることを増やす姿勢も参考になります。夏は勉強だけでなく、遊びや挑戦の時間にもしてみてくださいね。